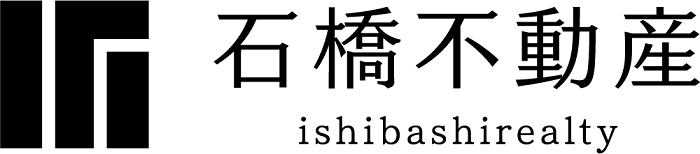新築建売住宅・新築一戸建て購入時にかかる費用の全て
建売住宅・新築一戸建てを買うときには、物件価格以外にもかかる費用があります。この記事ではそれぞれの費用について解説します。
基本的にかかる費用明細は次の通りです。必要な費用は物件価格3,000万円、住宅ローンを利用する場合の概算となります。
| 項目 | 必要な費用 |
|---|---|
| 物件価格 | 3,000万円 |
| 仲介手数料 | 100万円 |
| 売買契約書印紙 | 1万円 |
| 登記(表題・所有権保存・抵当権設定) | 40万円 |
| 住宅ローン関連 | 75万円 |
| 固定資産税・都市計画税精算額 | 5万円 |
| 不動産取得税 | 0~3万円 |
| 火災保険・地震保険(5年) | 15万円 |
| オプション工事 | 30万円~ |
| 家具・カーテン・家電・引っ越し | 必要な場合 |
こうして一覧にすると、物件価格以外にもいろいろな費用がかかるといのがわかりますね。3,000万円の物件を買った場合、必要な費用を含めると3,300万円くらいになります。もちろんこれは一般的な費用の概算なので、購入する物件、地域や利用する金融機関など、それぞれ個別の事情により費用は変わってきます。通常、費用は物件価格の6~10%くらいになります。
この記事ではそれぞれの費用についてある程度詳しく解説しているので、少し長くなっています。すぐに全部読む時間が取れない方は、諸費用を10%と考えて物件価格に1.1を掛けた金額を総費用と考えるということもできます。新築建売住宅の検討を始めたばかりなら、概算として利用できると思います。実際に物件が決まって購入を真剣に考える場合は、不動産会社等に相談して詳しい費用明細をもらってください。
それぞれの費用についての解説
物件価格
物件価格はいわゆる不動産の価格で、新築建売住宅の場合、土地と建物の価格のことです。一般的には敷地内の砂利敷、駐車場土間コンクリート、ポストなどの一定程度の外構工事も含まれた価格となっています。また、基本的に消費税込みの表示となっています。3,000万円という価格がついた新築建売住宅ならば、消費税込みの3,000万円という意味になります。
仲介手数料
仲介手数料は不動産会社に支払う報酬となります。仲介手数料は法律により上限が定められています。上限価格は不動産の価格(売却価格)に対して次の計算方法で求めます。
売却価格(消費税含まない)×3%+6万円+消費税10%
※物件価格800万円以下の場合は別途規定があります。
ポイントとしては、計算の基となる不動産の価格(売却価格)は消費税を含まない価格であるということです。不動産の価格3,000万円の内訳が次の場合の計算で考えてみましょう。
不動産の価格3,000万円
内訳 土地1,350万円 建物1,500万円 建物の消費税150万円
※土地に消費税はかかりません。
仲介手数料
土地1,350万円+建物1,500万円=2,850万円
(2,850万円×3%+6万円)×1.1(消費税10%)=100万6500円
この場合、仲介手数料の計算の基となるのは、3,000万円ではなく2,850万円になるのでご注意ください。
売買契約書印紙代
印紙税法では課税文書に既定の金額の印紙を貼って印紙税を納付することが定められています。不動産売買契約書は印紙税法の課税対象となる課税文書です。
印紙税は課税文書に記載された金額により税額が変わります。また、不動産売買契約書、工事の請負契約書、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)など、課税文書の種類によっても変わります。
ここでは新築建売住宅で多い価格帯の不動産売買契約書に必要な印紙税額を紹介します。
1千万円を超え5千万円以下のもの
本則税率2万円 軽減税率1万円
5千万円を超え1億円以下のもの
本則税率6万円 軽減税率3万円
平成26年4月1日から令和9年3月31日までは軽減税率の対象となります。
その他の価格帯や別の課税文書の印紙税が知りたい方は、「契約書 印紙代」とインターネットで調べてみてください。国税庁のホームページで詳細を確認することができます。
登記費用
新築建売住宅を購入した時に必要になる登記は次の3つです。
- 建物表題登記(表示登記)
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合)
建物表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記と抵当権設定登記は司法書士という国家資格を有する専門職の方が行います。通常、新築建売住宅の場合、土地家屋調査士、司法書士は売主が指定します。
建物表題登記
建物表題登記は建物が建ったときに、建物の存在自体を国に登録する業務になります。新しくできた建物の用途や構造、面積などが登録されます。表題登記には申請書や既定の図面が必要です。必要な申請書類や図面などは土地家屋調査士が作成して、法務局で登記申請を行います。
所有権保存登記
所有権保存登記は、建物表題登記で登録された建物の所有者が誰なのかを登録する登記になります。こちらの登記は司法書士が行います。費用については、主に3つあります。登録免許税、司法書士の報酬、必要な諸経費です。
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、住宅ローンを利用する場合に、土地と建物に抵当権を設定する登記になります。担保をとるという言葉を聞いたことがありますか。抵当権とはわかりやすく言うと、銀行がお金を貸す(住宅ローン)ときに、もし借りた人が返済できなかった場合にそなえて、土地と建物を担保にするということです。言い換えれば、銀行は土地と建物を担保にお金を貸すということです。もし住宅ローンの支払いができない場合、銀行は抵当権を実行し、土地建物を競売にかけて、優先的に債権(貸したお金)を回収します。
登記にかかる費用
表題登記は通常10万円前後になります。
所有権保存登記と抵当権設定登記にかかる費用は、主に次の3つの費用の合計になります。登録免許税、登記を行う司法書士の報酬、登記を行う上で必要な諸経費。金額は3,000万円くらいの新築建売の場合、約30万円くらいになります。登録免許税というのは、不動産の評価額や住宅ローンの借入額に既定の税率をかけて計算するので、土地の評価額、建物の評価額、住宅ローンの借入額によって変動します。
3,000万円くらいの新築建売住宅の場合、登記費用は合計で40万円くらい必要になります。
住宅ローン関連費用
住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。現金で購入する場合はかかりません。
住宅ローンにかかる費用には主に次のようなものがあります。
- 保証料
- 住宅ローン事務手数料(融資事務手数料)
- 印紙代
借入先の金融機関によってはその他にも費用がかかる場合があります。団体信用生命保険料については、通常は金利に含まれます(プランによっては金利上乗せあり)。
住宅ローン関連費用はどこで借りるかによってかなり幅があり、年収や勤続年数、お勤め先などによっても変わってくる場合があります。
一般的には2~3%くらいになります。3,000万円かりるのであれば、70~80万円になることが多いと思います。
例えばある銀行では、住宅ローン事務手数料が55,000円、保証料が60万円、その他の費用が数万円などです。また、保証料はかからないけど、住宅ローン事務手数料(呼び方はいろいろ)が借入金額の2.2%程度かかる銀行もあります。
どこで借りるかが決まっていない段階での資金計画では、いったん借り入れ予定額の3%くらいが住宅ローンに必要な費用と考えればよいでしょう。
固定資産税・都市計画税精算費用
固定資産税、都市計画税は1月1日時点で不動産(土地・建物)などを保有している人に、市町村等が課税する地方税です。都市計画税がかからないエリアもあります。1月1日時点での不動産所有者に4月から5月くらいに納税通知がきます。税額は不動産の固定資産税の課税標準額に規定の税率を掛けて計算します。固定資産税が通常1.4%、都市計画税が0.3%以内となっています。
たとえば不動産を3月とか6月に売却した場合、その年の1月1日時点での所有者に1年分の納税通知がきます。途中で売ったからといって市町村等が精算して売ったあとの日数分を返してくれるわけではありません。そこで不動産を引渡してからの1年間の未経過日数分は、日割り計算して買主から売主に精算金として支払うという不動産の商習慣があります。どこからどこまでを1年と考えるかは地域によって違います。通常は1月から12月を1年と考えるか、4月から翌年の3月までを1年と考えるかのどちらかになります。
精算金がいくらになるかは、土地の評価額がどれくらいか、新築住宅がいつ建ったのか、引渡日がいつなのかによって変わってきます。例えば1月1日時点での所有者に課税されるので、8月に建った新築を10月に買った場合、建物の固定資産税・都市計画税精算金はかかりません。また、これらの税金は固定資産税の課税標準額を基に計算するので、土地の評価が安いエリアと東京の中心部など評価がとても高いエリアではかなり違ってきます。
物件価格が3,000万円くらいのエリアだと通常は10万円あれば足りるでしょう。詳しく知りたい場合は、検討している新築建売住宅を販売している不動産会社に聞いてみてください。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した人に課税される地方税(都道府県税)です。地域によって変わりますが通常不動産を取得してから6ヵ月~1年くらいの間に納税通知が行われます。
新築建売住宅の場合は通常、不動産取得税の軽減措置が適用されます。土地がとても広くて評価額がものすごく高いなど、普通の新築建売住宅と違う場合を除いて不動産取得税はあまりかかりません。一般的にはかからない(0円)か3万円くらいになります。
火災保険・地震保険料
家を購入したあと、火災や地震で家が損傷したり崩れたりした場合に備える保険の費用です。通常、住宅ローンを組む場合、火災保険に加入することは条件とされます。もし住宅ローンを組んでいない場合でも、必ず加入することをおすすめします。
必要な費用は地震保険を付けるかどうか、その他いろいろな保証を付けるかどうか、保険金額をいくらにするか、年払いなのか長期(5年)一括払いなのかなど条件によって変わります。一般的には3,000万円の保険金額で15万円くらいになるでしょう。物価上昇などの影響で、保険料も上昇傾向にあるので、住宅購入検討時期に保険会社等に確認した方がよいでしょう。不動産会社に聞いても、ある程度の金額はわかると思います。
オプション工事費用
オプション工事費用に関してはかかる場合とかからない場合があります。例えば、新築建売住宅は建設する会社によって、網戸・カーテンレール・テレビアンテナが含まれていない場合があります。必要であれば、不動産会社等に依頼するか、自分で手配するかのどちらかになります。当社が営業するエリアでは、網戸・カーテンレール・テレビアンテナの3点セットで30万円くらいかかります。
また、キッチンのカップボードが欲しい場合やコンセントの増設、カーポートや物置などが欲しい場合などは別途費用がかかります。通常こうしたオプション工事費用も住宅ローンに組み込むことができます(金融機関による)。
家具・カーテン・家電・引っ越し費用
家具・カーテン・家電・引っ越し費用に関しては、人それぞれになります。今住んでいる住まいから持ってくる場合は、かからないでしょうし、新しくする場合は購入する費用がかかります。引っ越しに関しても、近くて荷物が少ない場合は、ご自身で軽トラを借りたり、親せきや友人に手伝ってもらう方もいます。
一般的に費用というのは人それぞれですが、100万円から200万円くらいかける方が多いという印象です。こちらの費用も通常住宅ローンに含めることができます(金融機関による)。
まとめ
新築建売住宅を買うときにかかる費用について解説しました。どんなご感想を持たれたでしょうか。いろいろとお金がかかるなあと感じる方も多いのではないでしょうか。
基本的にここで解説した費用に関しては、金融機関によりますが、住宅ローンに組み込むことができます。新築建売住宅の購入を検討する場合は、物件価格とその他の費用を考えて、実際に住宅ローンをいくら借りればいいのか、そして毎月の支払いがいくらになるのかを確認する必要があります。
また、住宅ローンを利用せずに現金で買う方も、本当にかかる費用、総額を把握することは大切だと思います。注文住宅でも同じです。”坪単価いくら”ではなく、オプションや外構、諸費用まで含めた総額がいくらになって、住宅ローンをいくら借りる必要があるのかを把握しておく必要があります。
新築建売住宅は大きな買い物であり、考えることもたくさんあります。その中でも、最も大切なことの一つがお金に関することだと思います。物件価格はポータルサイトや販売会社のホームページをみればわかりますが、総額はなかなかつかみにくいと思います。本記事が新築建売住宅を検討する方々のお役にたてばうれしいと考えています。