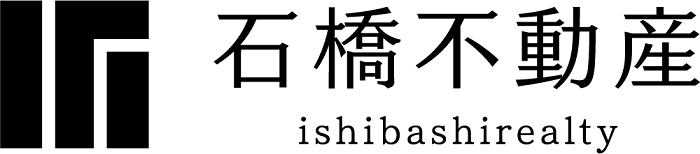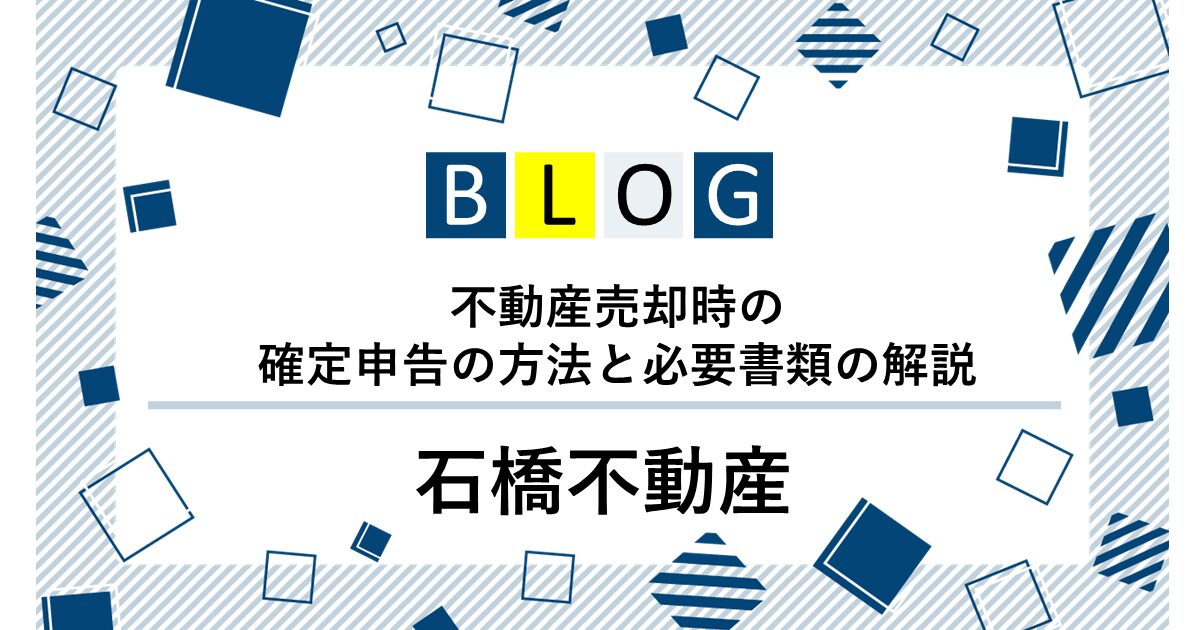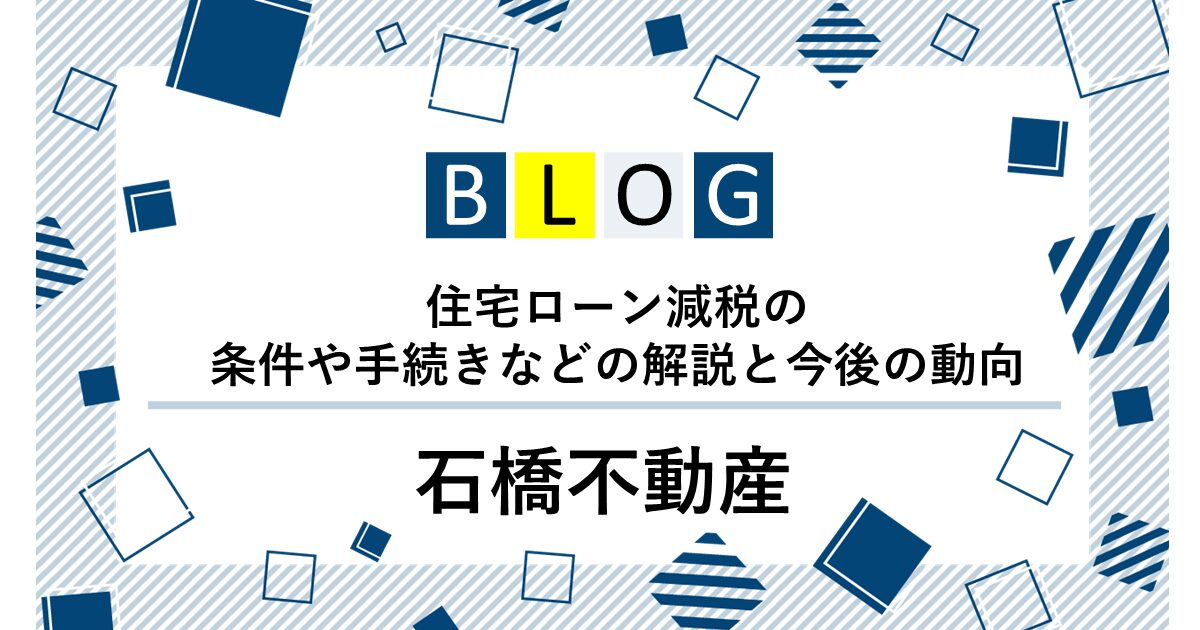土地や建物、マンションを売却して譲渡所得(売却益)がある場合は確定申告を行う必要があります。
不動産売却時の確定申告の大まかな手順は次にようになります。
この記事では確定申告の準備のやり方や、いつ行うのか、必要書類はどんなものなのかを解説します。
また、不動産売却をして、譲渡所得(売却益)が出ていない場合は確定申告の必要はありませんので、譲渡所得(売却益)があるかどうかの確認方法についても解説します。
不動産売却時の確定申告は、きちんと行わないと延滞税や重加算税などのペナルティを科される可能性があります。不動産を売却する場合は、確定申告についても正しく理解しましょう。
2026年の確定申告(2025年の所得)は2026年2月16日から3月16日までになります。
確定申告は譲渡所得がある場合に必要
不動産売却をして、譲渡所得(売却益)がある場合は確定申告を行う必要があります。
譲渡所得があるかどうか、どれくらいなのかは、正確には売却が完了した時にわかります。ただ、通常は売却前にどれくらいで売れたら、どれくらい譲渡所得があり、税金がどれくらいかかるかということを確認してから売却を進めることが多いでしょう。
ここでは譲渡所得の計算方法の概要を解説します。
譲渡所得の計算方法をより詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
石橋不動産ブログ 不動産売却時の譲渡所得についての解説と計算方法
譲渡所得の計算方法
譲渡所得とはわかりやすく言うと売却益のことです。何か物を売る商売をするときの粗利益が、不動産の譲渡所得にあたります。
不動産を売った時の譲渡所得は次のように求めます。
譲渡所得(売却益) = 不動産の売却価格- 取得費 ー 譲渡費用 ー 特別控除額(確定申告で適用)
売却価格はそのまま、売った価格のことです。契約価格とも言います。
取得費とは、売却した不動産を取得した時にかかった費用のことです。例えば、土地を元々2,000万円で購入していた場合は2,000万円が取得費の一部になります。取得費には他にも、購入時の登記費用や仲介手数料など様々なものがあります。
譲渡費用は不動産売却の時にかかった費用のことです。不動産会社に払う仲介手数料、契約書に貼る印紙代などがあります。不動産売却のために建物を取り壊した場合などは、解体費用なども譲渡費用となる場合があります。
特別控除額は条件に当てはまる時に使える控除額になります。居住用財産(マイホーム)を売却した時の3,000万円控除の特例などがあります。
注意点としては譲渡所得が出ても、特別控除を引けば譲渡所得がゼロまたはマイナスになる場合がありますが、この場合は確定申告の必要があります。確定申告を行うことで特別控除が適用されます。確定申告をしないと控除は適用されません。
譲渡損失がある場合
譲渡所得が出ない場合は確定申告の必要はありません。
ただ、譲渡所得がマイナスつまり譲渡損失がある場合、一定の条件に当てはまる場合は確定申告をすることによって得をする可能性があります。
通常、不動産の損益は給与など他の所得と損益通算することができない分離分離課税となっています。しかし、5年以上所有している居住用財産を売却して譲渡損失が出た場合、一定の条件を満たしていれば損益を給与所得など他の所得と損益通算できる場合があります。
対象となる場合、譲渡損失がある場合でも確定申告をすることでメリットがあります。
確定申告の必要書類
不動産売却をしたときの確定申告に必要な書類について解説します。
- 不動産売買契約書
- 不動産の取得費用を確認できる書類
- 不動産の譲渡費用を確認できる書類
- 本人確認書類
- 確定申告書第一表、第二表
- 確定申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
不動産売買契約書
不動産売却時の売買契約書を準備しましょう。
不動産売買契約書を申告書に添付して税務署に提出する必要はありません。売却時の金額など正確な情報を申請書類に記入するために使います。
もし見つからない場合は、通常不動産会社が写しを保管しているので、コピーをもらいましょう。
また、不動産購入時の売買契約書があれば、次に説明する取得費用の確認として使えます。
取得費用を確認できる書類
売却した不動産を購入した時の金額を確認するための書類になります。ものを販売するときに例えると、仕入れ額の確認ということになります。
不動産の場合は、実際にいくらで仕入れたとしても、証明する書類や、客観的な事実がわかるものがないと、取得費として認められません。
取得費を確認には次のようなものがあります。
- 購入時の不動産売買契約書
- 手付金、不動産売買代金の領収書
- 仲介手数料の領収書
- 登録免許税、登記費用の領収書(司法書士)
- 印紙代、不動産取得税の領収書や支払いを証明するもの
- 建物の購入費用、建築費用の領収書
建物の費用に関してはそのままの金額ではなく、所有している期間分の減価償却費を差し引いた金額になります。
譲渡費用を確認できる書類
不動産を売却した時にかかった経費の確認になります。
- 不動産仲介手数料の領収書
- 印紙代の領収書(売主負担分)
- 不動産を売るために片付けや草刈り等をした場合の領収書
- 土地として売るために建物を取り壊した場合の費用の領収書
- 貸家を売るために賃借人に立ち退いてもらった場合の立退の領収書など
- 土地を売るために支払った違約金や名義書き換え料などの領収書
不動産売却時の譲渡費用として認められるのは、売るために直接かかった費用だけになります。
修繕費や固定資産税、毎年やっていた草刈り費用などは維持管理費であり、譲渡費用とはなりません。
本人確認書類
紙の申告書を提出して確定申告をする場合は本人確認書類原本の提示またはコピーが必要になります。
マイナンバーカードがある場合はそれだけで本人確認書類として使えます。
マイナンバーカードを持っていない場合は次の2つが必要になります。
- 個人番号通知カードまたは、マイナンバーが記載されている住民票など
- 運転免許証または保険証などの身分証
e-Taxで確定申告をする場合は本人確認書類のコピーなどを準備する必要はありません。
確定申告書第一表、第二表
申告書第一表、第二表は確定申告をする人全員が必ず提出する書類になります。
第一表には収入金額、所得金額、控除、課税される所得額など基本的な情報を記入します。
第二表には所得や税額の内訳など、第一表に記載したことの詳細を記入します。
不動産の譲渡所得は第一表・第二表には記載しませんが、不動産の譲渡所得の確定申告の場合でも必要になります。不動産の譲渡所得は第三表に記載します。
申請書は税務署や地方自治体の税務課などで受け取ることができます。国税庁ウェブサイトからダウンロードすることもできます。また、税務署から郵送で取り寄せる方法などもあります。
事前に作成しておく場合以外は確定申告会場でもらって、書き方を教えてもらえばよいでしょう。
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産の譲渡所得や山林所得などに対する課税は分離課税となっています。
確定申告書第三表は分離課税の対象となる所得がある場合に提出する書類です。
入手方法は第一表・第二表と同じです。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
不動産の所在地や面積など基本的な情報、そして売却した金額や取得費、譲渡費用、譲渡所得などの情報を記載します。
書類は不動産売却後、税務署から送られてきます。また、税務署で受け取ったり、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
軽減税率や控除の特例を受ける場合に必要な書類
居住用財産(マイホーム)売却時の3,000万円控除の特例や、10年超所有軽減税率の特例などを受ける場合の確定申告では追加で必要になる書類があります。その他の特例にもそれぞれ追加で書類が必要になる場合があります。
居住用財産(マイホーム)売却時の3,000万円控除の特例
通常の不動産売却時の確定申告と必要書類は同じで、譲渡所得の内訳書に必要事項を記載して提出します。
ただし、マイホーム売却時の売買契約日の前日に住民票の住所が、マイホームの所在地と違う場合は、居住していたことを証明するために追加で書類が必要になります。
その場合の証明書類は、戸籍の附票の写し、または消除された戸籍の附票の写しなど、マイホームに実際に住んでいたことがわかる書類になります。
この特例について詳しく知りたい場合は「居住用財産の売却時に使える3000万円控除の特例について解説」をご確認ください。
10年超所有の軽減税率の特例
この特例を受けるためには追加で土地・建物の登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書は法務局またはオンラインで取得できます。オンラインの方が手数料が安くなります。
また、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」という長い名前の書類に不動産番号を記載して提出することで、登記事項証明書の添付を省略できます。
売買契約日の前日において住民票の住所がマイホームの所在地と違う場合は、3,000万円控除の特例と同様、戸籍の附票の写しなどが必要になります。
10年超所有の軽減税率の特例については「10年超所有軽減税率の特例のしくみと適用条件を解説」で詳しく解説しています。
不動産売却で損益が出た場合
不動産売却で譲渡所得(売却益)が出ない場合は、基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、一定の条件に当てはまる場合は、確定申告をすることで得をする場合があります。
通常は他の所得と損益通算ができない分離課税が適用される不動産所得ですが、条件に適合すれば特例で損益通算をすることができます。不動産所得の損益通算ができる特例は2つあります。
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
必要な書類は税務署や国税庁のウェブサイトで取得できるものと、自分で用意するものがあります。
詳細については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」 国税庁ウェブサイト
No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 国税庁ウェブサイト
確定申告の時期と場所
確定申告の時期
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。土日祝日であった場合は、次の平日になります。
申告の対象となる所得は前年の1月1日から12月31日までに得た金額です。
2025年分の所得の確定申告期間は、2月15日と3月15日が日曜日のため、2026年2月16日~3月16日までとなります。
基本的に土日祝は税務署等での申告や相談ができませんが、e-Taxを利用する場合は24時間申告できます。また、土日祝日でも申告を受け付ける日が設定される場合があります。
期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティ(加算税)が科されます。確定申告は申告期間内に行いましょう。
確定申告の場所
確定申告の場所は3つあります。自宅、各地の税務署、確定申告会場です。
e-Taxによるオンラインでの提出や郵送の場合は、自宅で確定申告ができます。
税務署での確定申告は、住民票所在地の税務署で行う必要があります。自営業の場合で事前に届出をしている場合は、登録した事務所の所在地を管轄する税務署で申告を行うことができます。
市役所や公的機関などで、申告期間に確定申告会場が設置される場合があります。こちらでも確定申告を行うことができます。詳細は各地の税務署に確認してください。
注意したいのは締め切りのタイミングがそれぞれ違うことです。
- 税務署・確定申告会場
最終日の17時
- 郵送
最終日の消印分まで
- オンライン(e-Tax)
最終日の24時
確定申告のやり方
確定申告の手順について解説します。
確定申告の所定の申告書などは税務署に行けばもらえるので、その他の必要書類を集めて税務署に行けば、相談員の方が丁寧に申告書の記載方法を教えてくれます。また、完成したらそのまま申告書を提出できます。税務に詳しくない方や、時間をかけて調べることができない方はこの方法をおすすめします。
確定申告について慣れている方や、税務に詳しく、パソコンやスマホの操作が得意な方はe-TAXで提出するのも効率的だと思います。
もちろん、自分で書類を作成できる方は郵送でも良いでしょう。
確定申告の手順
どの方法であっても、基本的な手順は次の通りになります。
譲渡所得がある場合、また損益があり特例が適用になる場合は確定申告を行う。
不動産売買契約書や本人確認書類は自分で準備する。確定申告書など所定の書式は税務署や国税庁のウェブサイトで取得。オンラインの場合はパソコンやスマホで作成。
税務署や確定申告会場で申告する場合は、相談員の方が記載方法を教えてくれます。オンラインや自分で作成する場合も、税務署等で相談することができます。
あとは期限内に確定申告を行いましょう。
また、確定申告手続きを税理士に依頼することもできます。プロにお任せすれば楽ですが、もちろん費用はかかります。
確定申告について
私も毎年確定申告をしています。そして毎年なぜか少し緊張します。
なぜでしょうね。
もちろん正しく申告していますよ。
納税は憲法で決められた国民の義務です。
皆さん、期限内にきちんと確定申告を行いましょう。
ちなみに私の場合、準備は妻がやってくれます。
軽く文句を言いながら。
妻には毎年感謝しています。