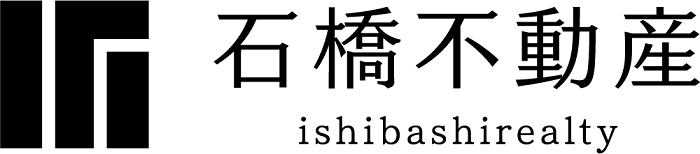不動産を売却しようとしたとき、建物が未登記、または一部未登記の場合はよくあります。この記事ではそのような場合にどうすればよいのかを解説します。
まずは、未登記の建物は売却できるのかどうかということを見ていきます。
答え できる場合とできない場合がある
- 買主が現金で買う場合 → できる(リスクあり)
- 買主が住宅ローンなどを利用する場合 → できない
次に、未登記の建物を売却する場合はどうすればいいのかをお伝えします。
答え 未登記のまま売るか、登記して売るか、解体して売るか。
- 買主が同意しており、住宅ローンも利用しない場合 → 未登記のまま売ることはできる(リスクあり)
- 買主が未登記のままでは買わない、またはローンの関係で買えない → 登記して売る、解体して売る
※現実的にはリスクのある未登記建物を買いたい人は少ないので、ほとんどが➋になります。
結論としては、未登記建物は未登記のままでも売主買主双方が合意して、住宅ローンなどを利用しない場合は売ることができます。また、未登記のまま売れない場合、買わない場合は登記をするか、建物を解体すれば売れるということになります。
ここからは未登記建物とはどんな建物なのか、なにが問題なのか、なぜ住宅ローンが使えないのかなど、いろいろな角度から、未登記建物の不動産売買について詳しく解説します。
建物が未登記とはどういう状態なのか
未登記の建物とは
未登記建物についてシンプルに説明すると次のようになります。
表題登記と所有権保存登記をしていないので、どんな建物であるかということや、誰の所有物なのかということが公的に登録されておらず、第三者に対して公的に所有権を主張できない建物。
通常建物を新築したときには、建物の所在地、用途、構造、大きさ(面積)などを法務局で申請手続きをして、建物の物理的な状態を公的に登録します。これを表題登記(表示登記)といいます。土地の表題登記もありますが、海を埋め立てて新たに土地ができた場合などのことで、通常の不動産売買には関係ありませんのでこの記事では説明を省略します。
表題登記を行うことは法律で所有者の義務となっています。新築した建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないことが不動産登記法で定められています。(不動産登記法第47条)
また、建物の増改築等を行って、建物の面積が増減したり、形が変わった場合も、その変更の内容を登記する必要があります。これを表題部変更登記といいます。
表題登記を行えば、どこにどんな建物があるのかということが公的に登録されます。また、表題登記のあとに、所有権保存登記を行います。表題登記はどんな建物なのかということを登録する登記ですが、所有権保存登記はその建物が誰のものであるのかという所有権などを登録する登記になります。
所有権保存登記は表題登記と違い、登記申請が法律で義務付けられているわけではありませんが、自分の建物であると公的に証明するためにも、とても重要な登記になります。所有権保存登記をしておかないと、第三者に対して法的に建物の所有権を主張できない状態になります。
一般的に表題登記は土地家屋調査士に依頼し、所有権保存登記は司法書士に依頼します。
未登記の建物とは、ここで説明した表題登記と所有権保存登記が行われていない建物のことです。現実に建物は存在していますが、どんな建物がどこにあるかということや、誰のものであるかということが公的には証明できない状態になります。
未登記建物のリスク
- 第三者から権利を主張されるリスク
- 住宅ローンなど、融資が利用できないリスク → 売れにくいリスク
未登記建物のリスクは、第三者に対して公的に所有権などを主張できないということです。
例えばある未登記の建物があるとします。それはAさんがお金を出して建てたものです。当然その建物はAさんのものですが、未登記の状態で、Bさんが「その建物は私のものだ」と主張したとします。もし、所有権保存登記をしていれば、登記事項証明書や登記識別情報(権利証)などがあるので、Aさんの建物であると証明しやすくなります。
また、Aさんがある建物を登記していないと、第三者に勝手に登記されてしまうというリスクもあります。登記申請は通常しっかりとした、申請書類や現地の確認等が行われるので、そう簡単に第三者が勝手に登記できるものではありませんが、やはりリスクはあります。地面師とかも普通はできませんが、時々ニュースになっていますよね。
もしAさんの建物を、第三者が自分のものだと主張したり、勝手に登記した場合でも、客観的な証拠を集めて裁判で争えば、Aさんのものだと証明できる可能性は高いでしょう。でも、そんな面倒なことをしたくはないですよね。建物を新築した時にきちんと登記して、そんなリスクは回避するべきでしょう。
また、相続した不動産が登記されていない場合はもっと複雑になるかもしれません。
例えば父親の土地・建物を相続した場合で、建物の一部(倉庫など)が未登記のままだったとします。お父さんの土地の上にあり、お父さんが使っていたので、登記されていないけどお父さんんのものだと思っていたとします。ところがある時、近くに住むBさんが、その倉庫はBさんのものだと主張してきました。もともとお父さんも了解済みだったと主張します。登記してないので、公的に証明はできません。どうなるかは細かい状況によりますが、こんな状況になったら非常に面倒ですよね。
さらに、未登記のまま売った建物がそんな状態になったらどうしますか。もう考えたくないですよね。
このように未登記の建物にはとてもリスクがあります。売主にも、買主にも、そして不動産業者にもリスクがあるので、通常みんな避けたいと思います。
当然このような未登記建物があれば、金融機関は住宅ローンなどの融資を出しません。基本的に未登記建物があれば、金融機関は融資をしないと考えていいでしょう。なぜなら、金融機関は建物を含めた安全な財産である不動産を担保として(抵当権を設定して)お金を貸すのですから、誰のものだかわからないものを担保としてお金を貸すことはできないのです。
未登記建物であるというのは、住宅ローンなどの融資を利用できない、つまり売れにくいというリスクもがあります。
未登記の建物は売却できるのかどうか
売ることはできるけど買う人は少ない
未登記建物自体を売買すること自体はできます。特に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、未登記建物のリスクで説明したような問題や危険性があります。不動産売却の場合は、不動産会社もリスクについて説明しますし、そんな状態で買う人は少ないでしょう。さらに住宅ローンも使えません。後で説明するようなケースではない限り、普通は売ることができないというより、そもそも買いません。
通常は建物登記を行うか、未登記建物を解体してから売却します。
建物未登記のまま売るのはどんなときなのか
未登記のまま建物を売るケースもあります。それは次のような場合です。
古家付土地の売却で、買主が家を新築する目的でその古家付きの不動産を買う場合があります。購入後にすぐ建物を解体する予定です。
通常は未登記建物の表題登記と所有権保存登記をして、さらに新しい所有者に建物の所有権移転登記をしますが、3回登記をする費用がかかります。でも3回も登記費用をかけてすぐに壊すというのは費用がもったいないですよね。このような場合は、建物は未登記のまま、所有権移転登記もせずに不動産売買をすることはあります。
この場合は、例えば売主が建物を解体して、その分の費用を売却価格で調整する場合もあります。売主、買主の意向などにより、いろいろなケースがあります。
あとは例えば、掘っ立て小屋のような簡易な倉庫で、土地家屋調査士に聞いたら登記できると言われた場合などは、買主が必要ないのであれば最初から壊して引き渡すという場合もあります。引渡しまでに壊せば、住宅ローンも使えます。
買取再販の不動産業者が未登記のまま買い取って壊したり、後で売主の協力を得て不動産会社の費用で表題登記と所有権保存登記をする場合もあります。
建物が未登記の場合の対応
未登記建物のリスクを回避するためには登記するか、未登記建物を解体する必要があります。特別な場合を除いて、未登記建物は登記するか、解体してから売却します。建物を新築した時に登記をしていても、増改築で形状や面積が変わっている場合は表題変更登記をします。
タイミングとしては、登記をする場合は売却が決まったらなるべく早めに登記を進めた方が良いでしょう。通常登記には2、3週間くらいかかります。相続した不動産や関係者が多い場合、複雑なケースなどは調査や書類を準備するのに時間がかかり、1ヶ月以上かかる場合もあります。
自分で登記する方法もありますが、専門的な知識が必要なので、通常は専門家に依頼して登記を行います。表題登記は土地家屋調査士に依頼して、所有権保存登記は司法書士に依頼します。
費用は通常10万円~20万円くらいになります。費用については、地域によっても差があるようです。
建物を解体する場合は、売却が決まってすぐに取り壊す場合や、契約から引き渡しまでの間に取り壊す場合があります。先に解体する場合は、不動産の売却が決まる前に解体費用が発生します。建物の大きさなどによりますが、解体費用は200万円~300万円以上かかることもあるので、いつ解体するかは売主の事情などによって変わってきます。
もし契約から引き渡しまでの間に建物を解体する場合は、契約書にいつまでに売主、買主どちらの費用で、そしてどちらが取り壊しをするのかを明確に記載します。また、契約から引き渡しまでの期間の設定については注意する必要があります。解体工事などは、天気に左右されたり、依頼する業者がいつ工事ができるのかなどをしっかり確認しておく必要があります。一般的には少し余裕を持った期日設定をした方がよいでしょう。
まとめ
未登記建物の不動産売買について解説しました。新しい建物であれば未登記というのは少ないでしょうが、築年数が経っている建物では、未登記のままであることも珍しくありません。またよくあるのが、増改築をして表題変更登記をしていないという場合です。
未登記建物の不動産売買についてまとめます。
- 建物が未登記であれば様々なリスクがある
- 未登記の建物は売れにくい
- 未登記建物も手続きなどをすれば売却できる可能性が高い
建物が未登記であっても、ほとんどの場合は問題なく売却できる可能性が高いと思います。
不動産会社は未登記建物の売却の経験があるので、建物が未登記であっても、現状をしっかり確認して必要な手続きを伝えたり、より良い販売方法を提案することができます。お気軽にご相談ください!
ご相談、お問い合わせは電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
TEL. 0947-85-9710
お問い合わせフォーム